1.BADENDが存在しない
 | Steins;Gate 開発元:5pb. ニトロプラス 発売元:5pb. 発売日:09/10/15 企画原案:志倉千代丸 シナリオ:林直孝 | 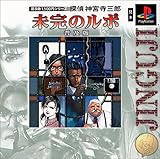 | 探偵 神宮寺三郎 未完のルポ 開発元:データイースト発売元:データイースト 発売日:96/11/29 ディレクター:西山英一 シナリオ:斉藤竜也 |
「Steins;Gate」や「探偵 神宮寺三郎 未完のルポ」のようにBADENDという名前のものは存在しないものです。そのなかでも2種類に分けられると思います。1つは「Steins;Gate」のように、trueEND or キャラクターエンドとなっているモノ、もう1つは「未完のルポ」のようにエンディングが1つしか存在しないものです。
前者のtrueENDとキャラクターエンドしかないというパターンですが、これらの中には悪い終わり方のものがないというわけではなく、名前こそキャラクターエンドでありながら「Steins;Gate」や「Memories Off」のような実質的にはBADENDのような作品も数多く存在し、パターン2やパターン3の派生といったほうがいいと思われるものもあります。また「Prismaticallization」のようにキャラクターエンドにはいるまで延々とループさせられるという、BADEND以上にBADな展開がまっているような非常に特異なパターンの作品も稀に存在します。
次に後者のエンディングが1つしかないものですが、こちらは「未完のルポ」以外では「レイトン教授シリーズ」や「ひぐらしのなく頃に」(やってないので確実ではありませんが)などもこれに近いと思われます。エンディングが1つしかないため選択肢があまり意味を持たないため、選択肢がなかったりあこれといって意味がなかったりして一本道だと批判されることがあります。そのため「神宮寺三郎シリーズ」のようにザッピングシステムを取り入れたり、「レイトン教授シリーズ」のように謎解き要素を取り入れることによってストーリーに矛盾の起きないようにゲームのボリュームを増やしている作品が多くみられます。
2.一応存在するがBADENDになる可能性は少ない
 | Ever17 開発元:KID発売元:KID 発売日:02/8/29 監督:中澤工 シナリオ:打越鋼太郎 |
「Ever17」のようにBADENDに入る可能性が非常に低く、BADENDがあってないようなものです。BADENDが存在しないものと並んで日常モノのADVに多いイメージを個人的には持つのですが、日常モノのADVはONE・Memories Off・Memories Off2しかやったことないのでこれといって根拠はありません。「Ever17」を見てみるとキャラクターエンドとtrueENDだけで完結しているので、BADENDはどっちつかずの選択ばかりをしていた事に対する天罰的な要素が強いのではないかと感じます。
3.ある程度存在しBADENDになる可能性が高い
 | かまいたちの夜 開発元:チュンソフト 発売元:チュンソフト 発売日:94/11/25 総監督:中村光一 監督:麻野一哉 脚本:我孫子武丸 |  | 銃声とダイヤモンド 開発元:ZenerWorks 発売元:SCE 発売日:09/6/18 ディレクター:佐々木真治 シナリオ:コバヤシヒロカズ 上杉直子 |
「かまいたちの夜」や「銃声とダイヤモンド」のようにクリアするまでにほぼ間違えなくBADENDを踏むようなもののことです。考えれば答えの出てくる推理ものに多く「なぜ間違えたのだろう?」と考えさせ複数回プレイさせることを意識して作られていると感じます。多くの場合選択肢毎にセーブをしていなくても間違えた場所の寸前から再度始められるようなシステムで作られている場合が多いです。
「12RIVEN」(例に上げた2つほどBADENDに入りやすい訳でもありませんが)のように選択肢毎にセーブをしていないとやり直しの効かないシステムであるにもかかわらず、BADENDに入りやすいためにストレスが溜り易い作品もあり、複数の選択肢が関わり合ったりBADENDに入ってからが長いゲームでは難しいシステムと思われます。
4.数が多いがあまり意味はない
 | 街 開発元:チュンソフト 運命の交差点 発売元:チュンソフト 発売日:98/1/22 監督:麻野一哉 シナリオ:長坂秀佳 |  | 428 閉鎖された渋谷で 開発元:チュンソフト発売元:セガ 発売日:08/12/4 監督:イシイジロウ シナリオ:北島行徳 |
「街」や「428」のようにBADENDが非常に多いもののことです。こちらもBADENDに入りやすく、その数が膨大であるため選択肢の寸前から再プレイしやすいようなシステムで作られている場合がほとんどです。
「街」や「428」ではBADENDを集めることによって隠しシナリオを解禁したり、一覧表を作ることによって残りの数がわかるようにするなど、BADENDを集めることに意味を持たせモチベーションが保てるよう努力されている場合が多くあります。
5.見ないと話がわからない
 | Remeber11 開発元:KID発売元:KID 発売日:04/3/18 監督・企画原案:中澤工 シナリオ:打越鋼太郎 |
trueENDを見るだけでは話の全貌が見えず、BADENDを見てやっと話の全貌が見えてくるというパターンです。エンディングを複数見せることのできるADV独特のシステムを存分に活用したものであると個人的には思っているのですが、BADENDの数が多すぎたりフラグがめんどくさかったりすると全部見るのが非常に大変になり匙加減が難しいパターンだと思われます。
ADVの独特さを最も利用したパターンなので好きなのですが、Remember11しかやった事がありません。そのRemember11もBADENDが非常に多い・複数の視点が互いに影響をあたえるためセーブ・フラグ管理がめんどくさい等システム周りに少々粗さを感じてしまいます。システム的にもう少し親切な設計がされていれば、また違っていればもう1ランク良い評判になったのではないかと思ってしまう個人的には最も惜しいと感じてしまう作品の1つです。
総論
当たり前のことですがBADENDに意味を持たせればもたせるほど、BADENDに入る可能性が高くなり、そこでストレスを溜めないための親切なシステムが必要になってくるものだと思われます。そのことを考えるとBADENDの地位の向上のためには素晴らしいシステムの登場が必要不可欠であるのではないかと感じられます。そこで個人的にはシステムが非常に親切であるチュンソフトやZenerWorksあたりが面白いことをしてくれるのではないかと思います。
また「Steins;Gate」はBADENDという名前のENDこそないものの、キャラクターエンドを見てこそ意味のある作りは、「かまいたちの夜」や「Remember11」を彷彿とさせる作りであるというのは非常に面白い試みであると感じます。そういう点では今夏発売予定の新作ADV「DUNAMIS15」なんかは一つ楽しみな作品となるのではないかと思います。

0 件のコメント:
コメントを投稿