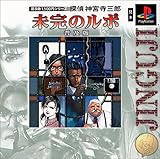第1回となる今回は1999年にアークシステムワークスから発売されたPrismaticallizationについて考察してみたいと思います。
 |
1999年にPSで、2000年にDCで発売されたループを題材とした恋愛ADVとなっています。ただし恋愛要素は他の恋愛ADVのなかでもに比べるととても少なく、また独特の文体、独創性に飛んだ非常に個性的なシステムのため一般的には奇作として扱われる場合がほとんどだと思われます。
アークシステムワークスによれば「多くの非難と僅かな賛辞を呼んだ」とのことであり、この言葉のとおり非常に粗い部分の多い作品でありますが、他の作品にない大きな魅力のある作品でもあります。
システムからの考察
「状態」を「記録」するかどうかという選択を出し、「記録」をすれば次のループで「開放」を行いその後の展開が少し変わるという独特のシステムとなっています。このシステムにより最短ならば15~20週程度で終わらせられる物もうまくやらなければ100週以上ループをしてもおかしくないという、ループ者を題材とした悪品の中でも周回数の非常に多い作品となっています。
シナリオからの考察
ループものでは多く見られるループからの脱出をテーマにしています。ただし、物語の展開に影響をあたえるのは前の世界での選択であり、現在の世界ではないため、多くのループものが現在の世界のみで脱出を試みるのに対し、"Prismaticallization"では過去の世界での行動に結びつくというのは他の作品と大きく違う部分ではないかと思います。
また、"Prismaticallization"では主人公はループを意識していません。他の作品の多くの主人公はループを意識した上で脱出をしようとするため、主人公とプレイヤーが同じ視点となりますが、本作でのプレイヤーは主人公視点というよりもフラグを管理する神様のような視点とも言えるかもしれません。
ADVからの考察
本作ではテキストは主人公目線で語られていますが、選択肢は主人公目線ではなく「状態」を「記録」するかどうかを決める神様のような視点から選ぶことになっています。この主人公視点でありながら、主人公の行動を直接選択しないというゲームシステムを自然に行っているのはこの作品の強みであり、ADVの強みではないかと個人的には感じます。
総論
シナリオ自体はループからの脱出というありがちな内容でありながら、独自のシステムによって他にない個性を持った作品だと思います。たしかに個性の強いシナリオ、場合によっては1周5分もかからないループが何十週も続ける展開により非常に人を選ぶゲームではあると思いますが、人を選ぶというのはそこに強い個性があるということの裏返しであると思います。
以下"Prismaticallizationとは関係の私事について
私の参加しているサークル「Moriyappoi」が、コミックマーケット80に参加します。頒布する作品は"街"のシルエットモードのような画面で展開する都市脱出型ノベルゲーム「The Dead」完全版となっています。近日中にサークルサイトリニューアルや体験版公開などを予定していますので、もし興味を持っていただけたなら、ついでにでもチェックしていただけると幸いです。よろしくお願いします。